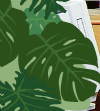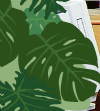|
 |
 |
 |
 |
 |
「今を生きる」ことはとても大変なことかもしれません。いつの時代にも違った苦労があるのでしょうし、その時代時代で人は悩み、考えながら歩んできました。では「今」私たちが抱える問題は何でしょうか? 物や情報が氾濫し、逆に何を選んでいいかわからない社会。おおっぴらかスマートに隠されているかはともかく、常に競争にさらされている社会。人と人との接点が希薄になった社会。いろいろに形容される社会の中で、私たちの心は揺れ動きます。家庭・職場・学校などで受けるさまざまなストレスは、それが適度であれば明日への活力となるでしょう。しかし、それが度を過ぎてしまうと私たちのこころは信号を発します。「眠れない」「気持ちが落ち込む」「怒りっぽくなる」「いつも不安である」「いくら食べても満足できない」などです。このような信号ははじめは小さく、「気のせいだ」などと自分も、周囲の人も考えがちです。しかし、このような状態をそのままにしておくと、いわゆる「こころの病」、たとえばうつ病・パニック障害・摂食障害などの病気に至る可能性があります。まずは「ちょっとこころの調子がへんだな」と思ったときに気軽にかかれる場所としてクリニックを開設いたしました。 |
 |
 |
 |
 |
「こころの病」とはどういう状態をさすのでしょう。私は「それしかない」という思考に陥ってしまった状態と考えています。「こころの病」といっても種類はさまざまです。しかし、こころの柔軟性が少なくなり、車のハンドルで言う「遊び」がなくなった状態であることにかわりはないと思います。うつ病ならゆううつな気分「しかない」、摂食障害なら食事に関する心配「しかない」、統合失調症の急性期なら幻覚妄想「しかない」などです。従って、治療の目標は「これしかない」を「あれもこれもある」状態に向ける事にあると考えています。
実際の治療は、薬物療法と精神療法が中心となります。薬に関しては「薬で性格がかわってしまう」とか、逆に「心の問題は薬では治らない」という質問をよく受けます。人は、通常でも一見自由に思考・行動しているように見えて、実は外的環境や自分自身の思考パターンに制約されているものです。特に、「こころの病」になると、病的な思考・行動パターンに強く影響されます。薬物療法は、この病的な思考・行動パターンを改善することで回復をうながすものであって、「性格をかえる」ものではありません。一方、薬だけでは充分ではなく、お話しをうかがい、どういった思考・行動パターンが生活する上での支障となっているかを同定し、どうすればいいかを共に考えていくことが必要です。これが精神療法です。しかし、どのような治療をするにしても、最も重要なことはより快適に日常生活を送れるようになることです。病気を治療していくことは当然ですが、それと同時に症状だけにとらわれず、皆さんと「共に歩む」姿勢で、何がその人その人にとって望ましいのかを一緒に考えながら診療にあたりたいと考えます。
「今を生きる」ことはそんなにたいへんなことではないかもしれません。もし社会や、それによって知らぬ間にできた自分のパターンを変え、「これしかない」を「あれもこれもある」視点でみることができれば。 |
 |
 |
 |
 |
「こころの病」は、今だ特別なものと考えられているのが現状です。しかし、実際はだれにでも生じうるものなのです。たとえば、WHOの報告では、人が一生のうちでうつ病にかかる割合は5人に1人とされています。また、ある時点での有病率も、百数十人に1人であって、とてもよくある病気と言えます。ただ、こういったところで偏見がすぐなくなるわけではありません。
希望はあります。自立支援法の制定で、曲がりなりにも身体障害、知的障害に加えて精神障害も同じ立場としてサービスを受けられる素地ができました。それまでは、精神障害者に対する施策は、他の2障害に比べて大きく立ち遅れていました。それに先行する形で、障害者スポーツでは、バレーボールが障害者スポーツ大会の中で行われるようになっています。いわゆる健常者と障害者が地域で「共に暮らす」ことの重要性はいろいろなところで言われています。私は、この地域で診療を行うことで、精神障害者がコミュニティのなかで「共に暮らす」お手伝いができればと考えています。
また、思春期の問題や、高齢者の認知症など、家族だけでなく、学校や地域、行政などコミュニティとして協力して支えていく必要がある問題についても積極的に取り組みたいと考えています。 |
 |
| ▲ページのトップへ |
 |
 |
| 医学博士 佐々 毅 |
精神科医、精神保健指定医、精神科臨床研修指導医、日本医師会認定産業医、日本体育協会公認スポーツドクター、日本救急医学会認定ICLS・BLSコースインストラクター。
平成4年東京医科歯科大学卒業。同大精神神経医学教室に入局。同附属病院神経精神科で精神科研修、日本医科大学高度救急救命センターで救急医学を研修した後、医療法人静和会浅井病院に勤務。精神科医長、外来部長の後精神科部長に就任。平成18年10月より新検見川メンタルクリニック院長に就任。臨床精神医学全般の他、薬物療法の最適化を含めた身体合併症予防、メンタルヘルスケア、特にアスリート・選手およびそれをサポートする監督・コーチ・トレーナーなどのメンタルヘルスケアを専門とする。
放射線医学総合研究所で精神疾患の画像診断の研究に従事。平成14年より日本スポーツ精神医学会の設立に参加し、現在理事をつとめる。平成18年9月に第4回日本スポーツ精神医学会総会・学術集会を会長として主催した。
平成27年より、疾患や障害のあるなしにかかわらずフットボールを通じて交流し、誰もが気兼ねなく過ごせるコミュニティーづくりを目指し、千葉『共に暮らす』フットボール協会を設立し、精神障がい者フットサルを中心に活動を行っている。
公益社団法人 日本精神神経学会
日本スポーツ精神医学会
公益財団法人 日本体育協会
千葉『共に暮らす』フットボール協会 |
 |
| ▲ページのトップへ |
 |